|
8月ワークショップ「親子でおもちゃづくり」
今月の子育てワークショップは「親子でおもちゃづくり」。
私たちの身近にある材料を使って、大人も子どもも楽しめるおもちゃを作りました。 講師は大津山琢さんです。 最初に作ったのは万華鏡。 なんだか作るのが難しそうですが、用意するものは紙コップ3つと黒い紙、文房具店などで取り扱われている分光シートだけです。 3つの紙コップは 1.のぞき穴を空け、そこに裏側から分光シートを貼りつける 2.底を切り取って筒状にする 3.底の部分を黒く塗る と、それぞれ少しずつ細工を施しておきます。 さて、まずは1と3の紙コップの外側に、ペンで思い思いの絵を描いていきます。 「何を描く?」「何色で描く?」と親子で話しながらデコレーションしていくと、とっても素敵な万華鏡の外側に! そして、筒状にした黒い紙を入れると万華鏡の内側ができあがります。 紙コップの内側の色がかくれるように黒い紙を入れる作業が意外と難しいようでした。 最後に3の紙コップの黒い底部分に、針を何か所か刺して小さな穴を空けます。 このコップを先ほどの貼り合わせた2に重ね、のぞき穴から見てみると― 「うわぁすごい!」「見えた見えた!」 子どもも大人も大興奮!きらきらと虹が輝く万華鏡のできあがりです! 次に作ったのはぶんぶんゴマと呼ばれるおもちゃ。 用意するものは牛乳パックの底を切り取ったものと紐です。 作り方はとてもシンプルで、牛乳パックの中心部分に2つ穴をあけ、そこに紐を通すだけ。 このコマは回し続けるのにちょっとコツが要るようで、みなさん悪戦苦闘。 大津山さんによると、コマを回すポイントは「自分の思う通りに動かそうとしないこと」で、これは子どもを育てる上でも大事なことだそうです。 世界に2つとない素敵なおもちゃができ、ワークショップは大盛況のうちに幕を閉じました。 |
|
月曜ロードショー 推手
シリーズ第733回
「推手」1991年/台湾映画/105分 Pushing Hands(1991/Taiwan/105min.) ※2回目の上映は、17:00〜@ホームギャラリーです。 |
|
「風を待たずに――」村上慧の実践3
出品作家の村上さんは、《移住を生活する》のほかに4点の映像作品も出品予定です。
そのうちの一つ《Watch and Forget》の制作を、熊本城二の丸芝生広場で行いました。 当日は青空が広がる快晴。熊本城周辺は、全日本中学校陸上競技選手権大会を控え、全国から来熊している選手や家族、外国人観光客などで賑わっていました。 《Watch and Forget》はこれまでにも世界の様々な場所で制作されているシリーズ。その場所にある建物などをホワイトボードに描き、描き終えたら真っ白に消すというプロセスを、コマ撮り撮影して編集した映像作品です。映像にはドローイング以外の物や音声も混ざり込み、村上さんが集中して描いている一方、周辺には様々な小さな出来事が起きては流れていく様子が伝わります。 今回は約90 x 190 cmの大きなホワイトボードに、熊本城二の丸芝生広場にある楠を描くことに。   写真を撮る観光客が行き交う中、村上さんはひたすら楠を自分の目で見て、手を動かしてなぞり、描いていきます。単体の建築物よりも自然の方が、動きもあり、非対称で、固有のものとして認識しにくく、安易にイメージとして定着しにくいように思えます。もしかすると《Watch and Forget》は、村上さんの体を通り抜けていくパフォーマンス作品とも言えるかもしれません。  炎天下、楠を5時間見続けて描き上げられたドローイングは、最終的にホワイトボードイレーザーのわずか数往復で真っ白に消されました。制作終了後に通りすがりの人から投げかけられた、「ええもん見させてもらいました!」という挨拶は、村上さんが楠を見続けたように、描き続けた村上さんを見た人の言葉に思えました。  村上慧《Watch and Forget》2017 GIII vol. 118 「風を待たずに――村上慧、牛嶋均、坂口恭平の実践」 会期:2017年 8月30日(水)–11月12日(日) 会場:熊本市現代美術館 ギャラリーIII+井手宣通記念ギャラリー |
|
三沢厚彦展 講演会「熊本市動植物園はいま」
「三沢厚彦 ANIMALS in 熊本」展の関連イベントとして、講演会「熊本市動植物園はいま」を開催しました。熊本市動植物園から獣医師の上野明日香さんをお招きし、2016年の熊本地震以後の熊本市動植物園の様子をお話しいただきました。
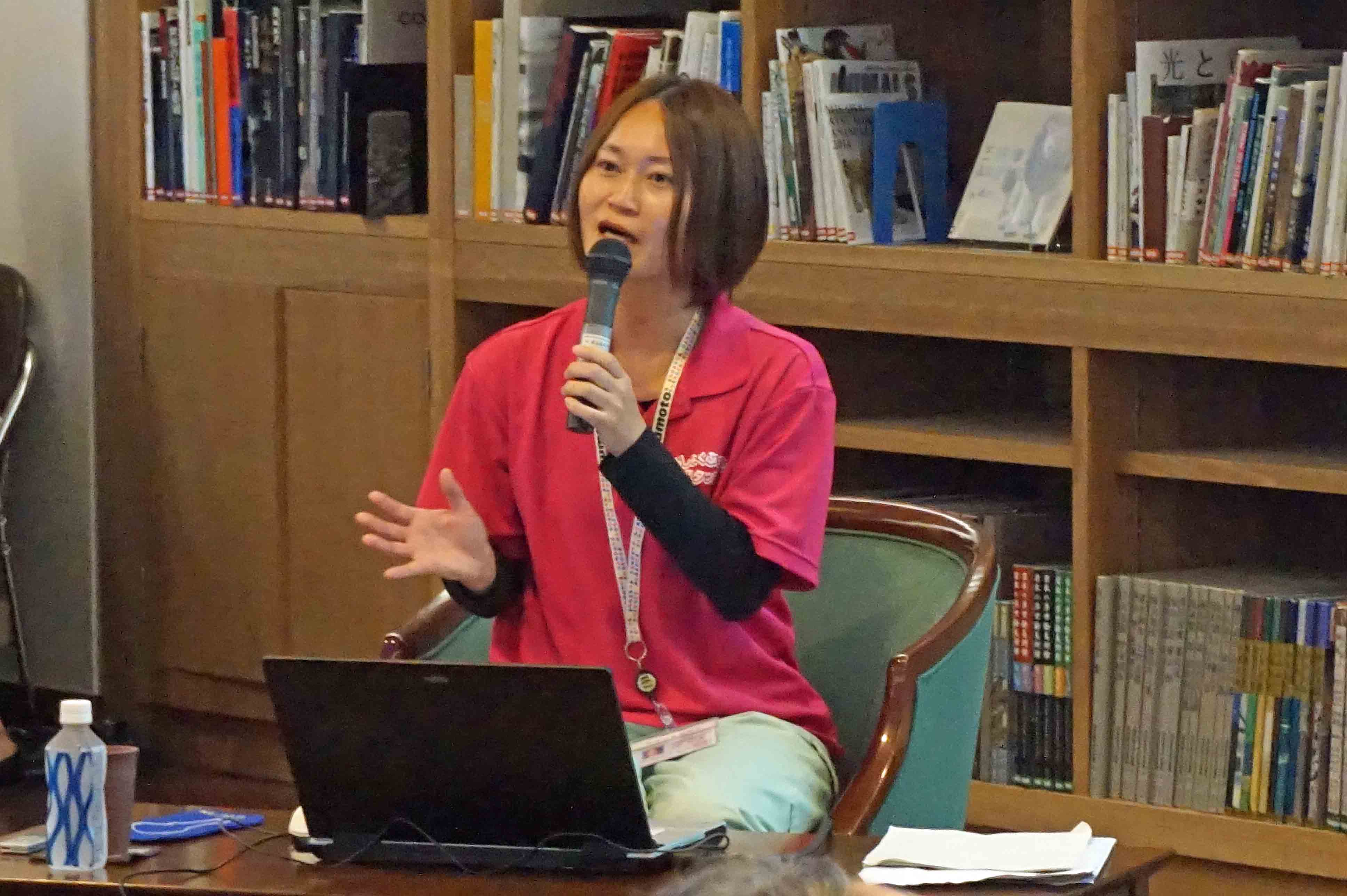 14日の地震後すぐ、上野さんは園の動物たちやスタッフの安否確認、設備の破損の状況確認や、「ライオンが逃げ出した」というデマなどに、余震がつづくなか対応していました。さらに、16日の本震によって、園内の液状化など状況は悪化。猛獣舎の被害のため、トラやユキヒョウなどを他の動物園に移動する準備するなど、スタッフの食料が少なくなっていることを後から気が付くほどに迅速な対応に迫られる日々だったそうです。 また、動物たちにも異変が生じました。カバは水に潜ったまま出てこなくなったり、クジャクは揺れるたびに鳴いたり、多くの動物は食欲が落ち、落ち着かない様子だったそうです。被災したときと同じ場所にいるのを嫌がるなど、半年間にもわたって異変が見られた動物もいたとのこと。そのため、普段のトレーニングを減らしたり、ケアに努めてきたことが紹介されました。  閉園中は、ブログで状況を伝えると、問い合わせを遠慮していた方たちも動物の様子を知ることができ、お客さんとのコミュニケーションが増え、スタッフも元気をもらうことが多かったといいます。部分開園を始めてから、多彩なイベントや閉園部分で暮らしている動物の元気な姿も紹介があり、ご来場いただいた皆さんもほっとした様子で話を聞いていました。 上野さんをはじめ、熊本市動植物園のスタッフがいかに動物を愛し、熊本地震以降も真摯に対応されていたかがわかる貴重な講演会となりました。 |
|
三沢厚彦展 スペシャル・ギャラリートーク
「三沢厚彦 ANIMALS in 熊本」展の関連イベントとして、「スペシャル・ギャラリートーク」を開催しました。熊本市動植物園から獣医師の上野明日香さんをお招きし、当館学芸員の坂本顕子とペアになって、展覧会をご案内しました。
 会場内の作品に合わせて、坂本学芸員からは素材や表現方法のお話を、上野さんからは、モチーフとなる動物の実際の生態について様々な話が紹介されました。 上野さんは動植物園にいる動物の写真を見せたり、実際のワニの皮などを触ってもらいながら、わかりやすく説明します。ウマグマの名前は馬のように走るところから名付けられたとか、ライオンのたてがみは敵から首を守るためという説があることや、象は相手の口に鼻を入れて会話をするなど、今まで知らなかった動物の習性を知るたびに、会場からは「おお〜」と声があがります。  印象的だったのは、アニマルズシリーズが実際の動物と共通する点と異なる点です。 たとえば、クマは鋭い爪や牙をもち、肩が発達しているため立ち上がって行動するのが得意。今回展示している作品たちも、立ち上がっていて、鋭い爪をもっています。一方、アニマルズシリーズはブルーやシルバーといった神秘的な目の色が特徴的ですが、実際にそういった目の動物はいないとのこと。 実際の動物の生態の話を聞きながらだと、さらに愛嬌が増して見えたり、作品の独特な目の色が際立って見えたりと、普段のギャラリートークとまた違う見方の変化に、ご参加の皆さんも夢中になっていただけたようでした。 |

